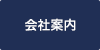⑱滋賀医科大付属病院が取り組む 産科オープンシステム「需要は無し」
専門家の継続ケア「LMC制度」があるニュージーランド。妊婦の9割が自分を担当する専門家に助産師を選ぶが、その多くが出産場所として「オープンシステム」が利用できる病院を選ぶそうだ。地域の開業医や助産師に、病院が分娩室を開放する取り組みだ。
このシステムを、県内では滋賀医科大付属病院が2005年に採用している。
母子診療科の村上節教授によると、オープンシステムの開設には、次のような目的があった。
地域の診療所と連携し、ハイリスク症例を大学病院へ振り分ける道筋を作る▽分娩をやめた開業医に分娩立ち合いの協力を求め、大学病院の産科医不足対策とする。
ただ、実際にシステムを使ったのはこれまでに医師3人。過去15年間172分娩中、医師が立ち会ったのが97件。そのほかの分娩の多くはハイリスク症例で病院の医師が担当したという。今年度は医師15人、助産師4人がシステムに登録しているが、実際にいまも利用しているのは医師1人だけである。
村上教授は「これまで分娩ができる診療所が地域に多く存在してきた。妊産婦にとって地域で健診を受けて、出産だけ遠方の病院へ行くというのは気が進まない。医療者も自分の施設に比べて自由度の低い病院は使いづらい。妊産婦にとっても医療者にとっても利用しづらい制度なのだろう」と分析する。
現在では、診療所の医師もハイリスクは事前に基幹病院に振り分ける体制が定着した。2024年に働き方改革が実施されれば、集約化された病院には医師の数が集中し医師不足も解消される見通しだ。村上教授は「オープンシステムは当初の役目を終えている」として、近い将来このシステムを終了する予定という。
それを聞いて、私はショックを受けた。オープンシステムは、妊娠初期から信頼関係を築いた開業助産師と一緒にお産に臨める安心感と、万が一のことがあればすぐに病院の医療的措置を受けることができる安心感の「二つの安心」を同時に得ることができる「良いとこどり」の仕組みだと思っていた。地域の診療所が次々とお産をやめていく中で、この仕組みは今後多くの妊産婦に求められていくのではないかと期待していた。村上教授は「助産師の利用はこれまでになく、妊産婦側からも需要はないと考えていた。貴方の話を聞いてそういう使い方もあるかも知れない」と私の意見を受け止めてくれた。
(8月11日掲載)
⑲自立した助産師が活躍する時代に
滋賀医科大学付属病院が2005年から続けてきた、地域の開業医や開業助産師に分娩室を開放する「産科オープンシステム」。診療所が減り、病院の集約化が進む中で、妊産婦の身近な存在として開業助産師のお産を見直してきた私は、出産場所に病院も選べるなら、万が一の事態を不安に思う妊産婦の積極的な選択肢となるのではと期待した。しかし、これまでにこのシステムを利用した助産師はおらず、妊産婦にも需要がないとして近い将来終了する予定だという。
私は、むしろ各地域の病院にも広がってほしいと思っていたと話すと、村上節教授は「それには医師も助産師も、妊産婦とその家族を含めた出産に関わるすべての人が『リスクを背負う』という意識改革が必要だ」と言う。滋賀医大では、緊急事態に24時間体制で対応できるマンパワーを備えた『最後の砦』の責務として、地域の助産師たちが開業するために必要な嘱託医・嘱託病院を引き受けてきた。だが、必ずしも他の病院がそうできる訳ではないという。
助産師主導のお産が急変するときは、必然的に難しい症例が起きたときだ。「難しい症例を急に引き受けるのは怖い」と考える医師は多い。確かに産科医は訴訟リスクが高い。緊急時の対応を望むなら、リスクを引き受けてくれる医師たちをフォローする仕組みを明確に示すことが必要だ。
村上教授は「本来、お産の7、8割弱は医師が積極的に手を下すことなく誕生する。健康な妊婦のお産を助産師が扱うことは法的に認められている」と理解を示す。「ただ、ローリスクと考えていた症例でも羊水塞栓症など様態が急変するケースがある。一旦起こればすぐに対応を始めないと落命してしまうような状況はいつ誰に起こるかわからない。妊婦さんは正しい情報を知識として得てリスクを判断し、自らの進む道を決めてほしい」と話す。
その上で村上教授は、働き方改革が施行される2024年以降は「自立した助産師が活躍する時代」とし、「減っていく診療所の代わりに、開業助産師が地域で活躍すれば、妊産婦にとっては出産方法や出産場所の選択肢を残すことができる。開業助産師が妊産婦一人ひとりと面で向き合い、長い距離をしっかりとみるのはよいことに違いない。院内でも、不足する夜中の当直などで『医師がいなくても私たちだけでできる』と言ってくれる自立した助産師が増えてくれたら」と期待をかけた。
早速知り合いの開業助産師にオープンシステムのことを報告した。彼女は「妊産婦の選択肢の一つとして是非残してほしい。予期せぬことで医療のバックアップを得たいと思っている人はいる。積極的に活用したい」と話した。
堀江昌史
(8月18日掲載)